11月16日、災害復旧の予算についての質疑
昨日具体的に書かなかったことを書いておきたい。
台風21号の最中、かつらぎ町は、井本町長を本部長に副町長と教育長も本部に詰めて陣頭指揮を執っていた。総務課長は衆議院の開票場の責任者になっていたので、災害対策からは離れていた。
19時15分にかつらぎ町は、紀の川流域を対象に避難勧告を出し、さらに20時2分には、かつらぎ町全域に避難勧告を出した。しかし、実際に指定した避難所は10か所しかなかった。町民の人口は1万7000人を超えている。10か所の避難所の設置では、全く町民全員を収容できないのに、どうしてこういう避難勧告の出し方ができるのか、理解に苦しむ。
この時の避難場所の1つに三谷こども園があった。三谷こども園は、紀の川の堤防の近くの低地にある。三谷地域の民家は、三谷こども園よりも高いところにある家が多い。どうして、紀の川の増髄による水害が心配されているときに、低地にある三谷こども園への避難を勧告したのか、三谷地域の人々は不思議に思ったらしい。
22時24分、今度は避難指示が出ている。紀の川浸水想定区域を対象にした避難指示だ。一体何軒、何人の町民を対象に避難指示を出したのか、11月16日の本会議で町長に質疑したが、町長は「今、資料を持ち合わせていないのでお答えできない」と答弁した。重要な判断をしたはずなのに、軒数と人口を記憶していないのは驚きだ。日本の災害対策の中で避難指示は、「ただちに避難して下さい」というレベルのもので、これ以上の発令は存在しない。つまり「避難命令」というものはない。避難指示の直後に、樋門を操作していた消防団員には、紀の川の水が堤防を乗り超す可能性が出てきたので、全員退避させている。
こういう切迫した状況のもとでも、新たな避難場所として開設されたのは妙寺中学校と笠田中学校だけだった。
ぼくの住んでいる折居という地域の樋門付近では「堤防まであと70㎝」(消防団員の後日譚)というところまで来ていた。
町長が、このような状況の中で職員に対し全員参集の命令を出したのは、11時15分頃だった。
「なぜ、避難指示が出てから40分以上たって全員参集の命令が出たのか。全員参集の命令を出してから避難指示を出さないと十分な対応ができないのではないか。順番が逆ではないか」
ぼくはこう質疑した。
町長は、「全員参集の指示はもっと早く出していたが、実際にメールで職員に指示を出すのが遅れてしまった。本部に入ってくるさまざまな情報に対応している中で、メールの手配が遅れてしまった」と答弁した。
いったい、何軒の家屋、何人の住民が避難しなければならなのかを判断して、避難指示を出し、それに対応するためにどれだけの職員を必要としたのか、その根本的な判断が全く見えない。このことを具体的に問いただしても、まともな返事が返ってこなかった。
スピーカーの付いた車による避難指示は、折居の場合11時30分を過ぎていた。
「避難指示が出ました。ただちに逃げて下さい」
放送は、こういうものだった。これ以外の情報は語らなかった。
住民は、避難指示の意味をきちんと理解していない人が多い。避難指示の後、避難命令があると思い込んでいる人もいるだろう。避難指示が、避難のために最後に発せられるものだという理解が極めて不十分だ。
そういうなかで、たとえば、「消防団員は、樋門から全員撤退しました。避難指示が出ました。全員避難して下さい」
こういうように伝えれば、もっと多くの人が避難していたと思われる。
「避難指示が出ました。ただちに逃げて下さい」
この情報だけで避難した人は少なかった。現実問題として、紀の川の水が堤防を乗り越え溢れ出し、それをきっかけにして堤防が決壊する可能性は、現実に存在した。こういう事態を想定しての避難指示だったはずだ。
ぼくは、質疑の中で「今回の緊急時、災害時の対応がどうであったのか徹底的に検証していただきたい」と訴えた。あまりにもずさんな対応だったと言わざるを得ないと思う。
この全体のアウトラインを聞いた後で、さらに西渋田谷川の樋門と島地域で発生した水害についても問いただした。9時過ぎにBさんが自主的に避難し、腰まで水に浸かって堤防に上がり、樋門捜査員である消防団員のところにたどり着いたのは、9時30分頃だと思われる。
「町長は、Bさんが樋門捜査員のところまで逃げてきたという連絡を受けていたのかどうか」
この問いに対し、町長は「個々の状況は把握できていなかったが、全体の状況については把握していた」という趣旨の答弁を行った。
ものすごく遠回しな言い方だ。
腰まで浸かって逃げてきた人のことを個々の状況だという発言には怒りを覚えた。
「その情報は本部には伝わっておりません」
なぜこういう率直な答弁ができないのだろうか。
人の命に関わる事態をどう考えているのだろうか。
なぜ、消防団員は、Bさんたちのことを伝えなかったのか、それとも伝えたのか。伝えたのに本部までその情報が届かなかったのか。この問題は、決して個々の小さな問題ではない。9時過ぎにものすごく水が増え床上浸水したことを避難指示がない中で起こっていたことを災害対策本部が知っていれば、本部の対応は明らかに変化していたのではないかと思われる。
島には、5つの企業があり、これらの企業は避難指示が全くない中でものすごく浸水している。工場が9時頃から10時にかけてすでにものすごい状況になっていたことを役場が知っていたら、島地域への避難指示はもっと速かったと思われる。工場の東側には民家があり、これらの人々への車のスピーカーによる避難指示は23時頃だった(住民の証言による)。
結局、災害対策本部は、紀の川の危険水位を拠り所にして、22時24分に避難指示を出し、そこから職員の力で避難指示を車で伝えるという対応をしたということになる。
これが、「個々の状況は把握できていなかったが全体の状況は把握できていた」ということなんだろうか。
今回は人命が失われることにはならなかったが、そういう状況が生まれていたら、町の責任は非常に大きいと思われるようなずさんな対応だった疑問がある。
本当に災害対策本部は、機能していたのか。こういうことまで疑われるような状況だった。
これが、ぼくが質疑した1つの側面だった。災害は自然によって引きおこされるが、災害への対応によって被害を抑えることはできる。そのためにこそ、災害時の応急対応が求められる。
かつらぎ町は、自らの対応を本当に自覚をもって検証することができるのだろうか。このことさえ心配になってくるような町長の答弁だった。

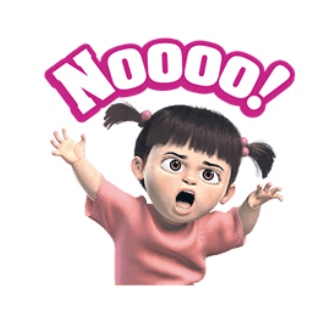










ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません