スーパー歌舞伎「ヤマトタケル」

妻がチケットで予約していたスーパー歌舞伎の「ヤマトタケル」を大阪の松竹座に見に行った。Tシャツで行こうと思っていると、スラックスとワイシャツ、革靴を履けと言われたので、議会に行くような格好で大阪に行った。林間に車を置き、電車で難波まで行行った。難波駅を(北かな)出たところに松竹座がある。雨が降っていたので、観光案内所で地下を歩いて外に出て、松竹座に行くという方法を採った。
25分ほど前に松竹座の前に着くと、多くの人が中に入ろうとしていた。スーパー歌舞伎のなんたるかを知らず、市川家をめぐるこの間の騒動もほとんど立体的には理解していない中、座席に着いた。演目が始まって1時間で休憩となった。そのときにネットで検索して、ようやく「ヤマトタケル」が3幕あり、第1幕1時間、第2幕1時間、第3幕1時間20分という長丁場だということを初めて知った。11時から始まり12時になると休憩になり、この30分で多くの人が持ち込んでいたお弁当を食べていた。2幕後の休憩は20分だった。結局、11時に始まって「ヤマトタケル」が終わったのは15時10分だった。4時間10分、松竹座にいたことになる。
舞台の仕掛けはすごかった。緞帳が上がり、宇宙と地球が映し出されたのを見て、これはどういう仕掛けかと言うことさえ、理解を超えていた。この宇宙と地球の絵は、照明を当てると後ろの舞台が透けて見えた。仕掛けの仕組みが見えない。舞台にはたえずドライアイスか何かで霧がかかっているような演出がなされていて、そこにスポットライト的な照明が当たると、それだけで色と光の演出が行われる。舞台の一番奥にもスクリーンがあり絵が掛けられたり、大仕掛けの舞台装置の中で大勢の役者が激しく動き回ったりした。回り舞台とせり上がる舞台、下がる舞台が、縦横に駆使され見るものを作品世界に引き込んでいた。
船で海を渡るシーンの波の描き方が圧巻だった。波を布で演じ、荒海を表現するのは、布の下に入った人間だった。船から畳を海に落とし、その畳が海に浮かぶシーンは、どうやって演じているのか分からなかった。
先日、演劇鑑賞会で「前進座」の公演があり、歌舞伎の学習をしてくれたので、拍子木の音の出し方や、音楽の奏で方、太鼓の音による風や雪の表現の違い、見栄の切り方、演者への声のかけ方などを教えてもらったので、それだけで歌舞伎を少し楽しめることができた。大立ち回りをしているときの、舞台の床に打ち付けて拍子木で音を出している人の姿を見た。演者の動きに合わせて、音を出すために集中している鋭い目が印象的だった。この音があるのとないのとでは、演技が全く違ってくる。
スーパー歌舞伎は、現代語をふんだんに取り入れたもので、見る側が作品世界に入るのを助けてくれる。今放映中の『光る君へ』でも現代語がたくさん使われているが、こういう言葉の取り入れ方は、スーパー歌舞伎の力によって実現したものかも知れない。
もともと歌舞伎は、江戸時代に民衆の中ではやっていた踊りなどを取り入れて演じて見せたところから始まっている。最も現代的な演技が歌舞伎の真骨頂だったので、歌舞伎の精神の一つは、現在流行しているものを取り入れて演じてみせるところにある。
スーパー歌舞伎を生み出した一つの大きな力は、梅原猛さんだったのは間違いない。この人の存在がなければ、古事記を題材にした「ヤマトタケル」は台本として書かれなかっただろうし、スーパー歌舞伎も生まれなかったのかも知れない。この人の存在がなければ、スーパー歌舞伎の出現はもっと後になったし、日本の古い神話が題材になることはなかったかも知れない。
作品は帝とその息子である「ヤマトタケル」の父子愛、とくに息子の側から父へに愛情が軸になっている。
ぼくにとっては父子愛と縁が薄い。父の存在はぼくが6歳までの話であり、同時に嫌な存在だったのでヤマトタケルのような思い入れというものが薄い。それだけに描かれた世界の意味をかみしめるのには時間がかかりそうな感じがした。
1日に2回公演をするということにも驚かされた。映画じゃないんだから、生の舞台、失敗が許されない点には、計り知れないものがある。それでも失敗はつきものだろう。そういうものを乗りこえながら長丁場を演じるエネルギーは、大きなものだと感じた。



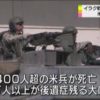
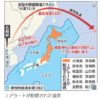






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません