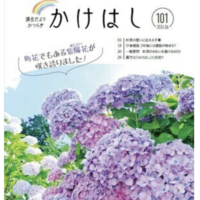「学芸会」と「八百長」
お昼前から議会だよりの一般質問原稿のまとめを行った。いつも苦労するのは1時間のやり取りを1000字以内に収めることだ。要約して話の筋だけ、結論だけを書く。実際の質問では、重要視した質問の結節点や論理の具体的展開を割愛せざるを得ない。どうしてこのような答弁を引き出すことができたのかというようなことは、記事の中には反映できない.
幸いなことにかつらぎ町議会も、議会の一般質問議事録をネット上に公開するようになった。平成30年3月と6月の一般質問が読めるようになっている。時間はないと思うが、議会だよりの記事と実際の一般質問との違いを見比べていただければ、その違いはよく分かると思う。
何度も書いてきたが、かつらぎ町議会の一般質問にはシナリオがない。当局との真剣なやり取りがきちんと一般質問に反映するようになっている。事前に質問と答弁が出来上がっていて、それを互いに読み上げるというような「学芸会」や「八百長」のような質問とは次元を異にしている。
「学芸会」や「八百長」のような、質問と答弁の出来上がった一般質問よりも、かつらぎ町の議会の方が、議員の質問が実現することが多い。シナリオのない真剣勝負の中で、予定していなかった変化が生まれるところに違いがある。当局の許容範囲の中で、当局の許可を得て要求が実現していく姿は、釈迦の手のひらの中で飛び回る孫悟空のようなものだ。
「答弁書が出来上がっている議会のやり方にも、いい面がある。どちらの方法にも長所と短所がある」というような言い方がなされたりするが、それは全く違う。
法律や条例という共通言語があり、それに基づいて事業を進めなければならない自治体にとって、逃げられない問題がある。議員からどのようなボールが投げられ、当局がどう打ち返すのかという真剣勝負のなかでしか明らかにならない問題がある。
真剣勝負なら逃げられないものになっても、事前に答弁書が出てきて、これでよろしいですかという議会では、当局が事前に結論を持って質問に臨むことになる。最近では、答弁書によって答弁された後も一問一答でさらに迫れるようになっている議会も生まれているが、質問を見ていると、「さきほど答弁したとおりでございますが」という域をほとんど出ない質問に終始する。
オリンピックにシナリオがあり、練習どおり、シナリオどおり試合が運ばれたら、誰が真剣にオリンピックを見るだろうか。試合のシナリオを互いに書いて、手の内を全部見せ合ってこう攻めたらこう反撃するのでよろしくというあり得ない世界が、地方自治体には当たり前のように存在している。
少なくとも国会のやり取りを見習うべきだと思う。
国会の予算質疑や総括質疑は、通告制を取っているし、活用する資料も公開されているが、質問をどう組み立てるか、どう展開するのかは議員の努力にかかっている。基本的にはかつらぎ町が実現している一般質問や質疑と同じだ。どうして、地方自治体の議会で国会と同じようなことが実現しないのか。一体、地方自治体というのは、どういう議会を実現したいのかがよく分からない。
徹底的に質問のすり合わせを行い、答弁書を作成し、それを事前に議員に見せて、互いに納得し、議場の外で質問前に今回の質問を通じてどこまで実現するのかを理解して、質問に臨むというのは、住民を視野の外に置いたものではないだろうか。
国会の質問を見ていると分かるように、議員の質問を通じて、事態が切りひらかれていく。議員が岩をこじ開けて真相に迫り、国民の願いの実現に貢献していく姿は、見ていて気持ちがいい。質問と答弁が事前に明らかになる一般質問を繰り返しても、隠したい真相に迫ることはできず、問題点を深くえぐることもできない。
かつらぎ町議会で実現している真剣勝負が、他の議会でも実現できるように。
原稿をまとめながらこういうことを考えていた。