帰納と演繹、具体と抽象
本屋さんで何気なく買った『賢い人の秘密』という本は読んでいる途中だが面白い。この本の第1部は「何を学べば賢くなるのか」をテーマに書いている。医学生は、医学を学ぶ中で帰納的な考え方に長けていくといい、法学部の学生は演繹的な考え方に長けていく。これは驚くべき面白さだった。
医学生は、具体的な患者の症状に触れて、それが一体どの病気から出ているのかをさまざまなデータに基づいて把握しようとする。ところが、法学生は、その事象が法律のどれに当てはまるのかを法律の観点から見定めていく。
医学生と法学生は考え方のベクトルが逆。
医学生は具体的な事象から共通項を見いだして病気を類推する。
法学生は、法律という定義から現実がそれに当てはまるかどうかをみて判定する。
医学生は帰納的考え方に長けていく。法学生は演繹的考え方に長けていく。この本ではそう書いていた。
学ぶ内容によって、物事に対する考え方のアプローチの仕方が変わってくるというのだ。
帰納というものの見方は、個別的な事象と個別的な事象の中から共通項を見いだすものの見方だ。演繹的なものの見方は、命題から出発して、個別的な物の中にその命題を見いだすというものの見方だ。
演繹的見方は、法則から出発して、個別的事象の中にそれを見いだすので、それが正しいという確信めいたものになる。しかしそれが果たして正しいのか。間違っていないのかという問は立てられる。これに対し、帰納的な見方は、個別的な事象から一般的な共通項を見いだすだけなので、証明しきれないもどかしさがついて回る。確かなことは言えないが、おそらくこういうことが言えるだろうというような感じになる。
こういう違いがあるので、ぼくは帰納的な見方を大切にしてきた。帰納的な見方をかなり確実視するためには、多数の一般的傾向を拠り所にする必要がある。ただし、帰納は帰納、演繹は演繹という風に分かれているのではなく、帰納と演繹という関係も、弁証法的に補完し合っているので、両方の見方を駆使しながら本質に迫っていくことが大事になる。
どちらも、抽象的な思考なしには成り立たない。具体的なもの、個別的なものから共通項を見いだすためにも、命題から出発して、具体的、個別的な事物の中から法則的な命題を導き出すためにも、抽象的な思考が必要になる。言い方を変えれば、具体的な事物の本質を把握するためには抽象的な思考なしには本質の把握はできないということを意味する。この抽象は、具体的事物から離れるような抽象ではなくて、具体的事物の中にある本質により一層迫っていくような抽象になる。
抽象とは何かという点で、見失ってはならないのは、具体的な事物の本質に迫る抽象というのは、具体的事物から離れる宙に浮いた抽象ではないということだ。この考え方が大事なのは、人間の思考は、客観的な事物を反映したものだが、必ず言語によって、思考される関係があるので、人間の思考による抽象は、現実から乖離しして、抽象による抽象が進み、事物から離れ、本質から離れる抽象が成り立ってしまうことがあるということだ。曲線は、思考によって直線に変化する。
本質に迫る抽象と詭弁に満ちあふれた抽象というものが、どうして発生するかということを知った上で、抽象的思考を活用することが重要になる。そのときに具体的事物と抽象との関係を知ってるのと知っていないのとでは、違いが生じる。ほんものの抽象が、具体的事物の本質に迫る力をもっていることを知っている人は、知らない人と比べると、迷路に迷うことは少ないだろう。
本を読みながらそんなことを考えた。


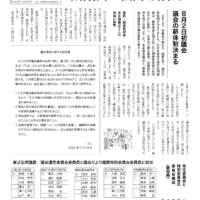








ディスカッション
コメント一覧
『頭のよさとは何か』は読了した。まあまあである。
『賢いひとの秘密』は半分程読んだ。これはなかなかの本ですね。ラテン語を学ばなくてはならんとはちと面倒臭いが頑張って挑戦してみるか。そういえば俺の師と仰ぐ先輩はラテン語、ギリシア語、英語がペラペラで、国内では翻訳者が居ない壮大にして貴重な本を翻訳して(只でネット上で)公開している人物がいる。然も分厚い古典を翻訳しているのだ。此れは現在進行形だ。俺も読んでみたが難解極まりない。匙を投げだしたくなる内容だ。翻訳者が居ない訳だ。
『頭のよさとは何か』は和田秀樹さんが1人でしゃべっている様な印象を受けた。中野信子さんにももっと喋って欲しかったな、という気持ちが湧いた。対談本だったんですね。
さて、明日は大晦日だ。今日は小晦日である。俺は明日から凄いスケジュールで忙しくなる。という訳で、東芝さん、今年も色々と御世話になりました。いい御年を御迎えください。
なんまいだ。
あ、最近、コメントが激減しておりますが、俺のせいかな?
コメントではなく、アクセス数であった。
『頭のよさとは何か』という本は、そんなに深くない本ですね。社会科学の視点が弱いので、その分野の発言には、頭のよさがあんまり発揮されていないというパラドックスめいた点もありました(笑)。『賢いひとの秘密』は、ぼくもまだ途中ですが、次第に面白くなる本ですね。楽しんで読みたいと思います。
アクセス数の激減は、おそらく役場が休みになって職員の方々がぼくのブログから離れているからだとも思います。もう一つは、世間のブログ離れ。200を超えるアクセススが100程度か100以下になってしまいました。Facebookはまだ文章を書いていますが、Twitterは短いので、かなり人間を破壊するものだと思います。
よいお年を。来年もよろしくお願いします。今年はお世話になりました。