庁舎建設検討委員会と基本条例の見直し
庁舎建設検討委員会の会議
午前中は庁舎建設検討委員会が開催された。秘密会という話は提案されなかった。2年間の債務負担行為を認めて伴走型の支援を行うためのプロポーザルが行われ、オリエンタルコンサルタンツ和歌山事務所が最高得点者となった。この結果は町のホームページにも公表されている。しかし、伴走型の支援の期間は1年9か月しかない。この間にモデルを作成し、庁舎の姿をこのモデルによって明らかにしつつ、同じ敷地内に賑わいをつくるための商業施設をつくるということを、市場調査を行いながら成し遂げられるのかという疑問が湧く。1年9か月は短い。
期間を設定するのは町の側。果たしてかつらぎ町は、そういう基本的な枠組みをどこまで深く認識し、業者選定に入ったのかという点で疑問がある。町職員の体制の弱さがあるので、庁舎建設のプロジェクトチームを5人程度でつくる必要があるが、そういう体制は組めないという認識が町長から示された。
技術のともなう仕事において町当局にノウハウがないとなると、相手方は町側を低く見て態度を変えてくる。ぼくはそう思っている。したがって今の進み方に心配がある。
同じコンサルタント会社が、○○市とかつらぎ町の福祉関係の事業計画に対し、委託を受けたことがあったので、2つの自治体の計画の比較を行ったことがある。調査を始めると「○○市は計画を作成するのが大変だったが、かつらぎ町は楽でした」ということを教えてもらった。確かにその市と本町の計画の中身は全然違った。
これとは別の福祉の計画策定のとき、ぼくは審議会のメンバーだった。計画策定の審議会の席に、コンサルタント会社が入り答弁を担ったことがあった。事業計画を作成したのはコンサルタント会社なので、この会社に説明をしてもらうというのが町の態度だった。これはひどいと感じた。かつらぎ町名で事業計画をつくるのに、町は説明さえできないということだった。
こんなひどいことは、今のかつらぎ町には、皆無だと思っている。しかし、現在の町のいろいろな計画を読ませてもらっても、いい計画だというものがどれだけあるだろうか。それは心許ない。
最近つくられた長期総合計画では、町の現状認識が全く示されなかった。現状認識があって計画があるのが普通であり、それは総論部分に書かれるものだが、町はあえて総論部分を書かなかった。書かなかった理由は、書いても読んでもらえない。計画の本文から読んでもらう方がいい。というものだった。こういう理由で現状分析を書かないというのはいかがなものだろう。
「総論部分を書くべきではないか」ということを指摘したぼくの提案は採用されず、総論のない長期総合計画がつくられた。これはぼくにとって悲しい現実だった。
コンサルタントによる伴走型支援で事業計画のモデルが作成される。町はコンサルタントと肩を並べられるように努力してほしい。そうしないと計画はいいものにならない。ぼくは本気でそう認識している。
総務課と基本条例で懇談
午後は基本条例に対する総務課との懇談。実際に条例を作っている担当とのヒアリングは楽しい。条例をどう書くのかというのは、自治体ごとに微妙な違いがあると思う。しかし、各自治体には、長い戦後の歴史の中で積み重ねられてきた到達点があり、文章の書き方がある。ぼくが今行っている議会基本条例の見直しは、この町条例の中に基本条例を組み込む作業でもある。
今までの議会基本条例は、そういうものには、なっていなかった。全国の議会基本条例にも、条例体系とは全く異なる傾向が数多く存在する。これは一つの考え方だろう。堅苦しい条例の体系から離れて、議会基本条例をつくる。この考え方で前文がですます調だったり、本文もですます調で書かれているものもある。
ただしぼくは、こんなものをつくると、実際の議会運営の改善さえうまくいかないと思うし、これを行政側が見たときに、議会に対する信頼を損ねる結果を生み出すと思っている。議会は行政に対するチェック機能を果たさなければならない存在である。自らが作成する議会基本条例さえまともに作れない集団が、どうしてチェック機能を果たせるのか、議会という集団は条例さえ読めないのかと思われる。それは恥ずかしい気がする。条例や法律の書き方が難しいといい、変えるべきだというのであれば、すべての法律や条例を変えるまでたたかえといいたい。それをしないで、議会基本条例だけ平易にする意味はない。
二元代表制の一翼を担う議会は、ある意味で町長の側と対等平等だ。そのためには、行政と同じ土俵に上る必要がある。議会基本条例をつくる作業というものは、行政の側から見てもいいものができたと思われるよう努力しなければならない。
議会にも条例や規則や規定、要綱がある。議会基本条例が議会の最高の理念を示すものであり、実際の議会運営の改善を図ることを目指すのであれば、当然、会議規則や委員会条例との整合性を図る必要がある。議会基本条例を作って、会議規則の改正を行わないと、基本条例に書いていることと会議規則との間に齟齬が生じる。基本条例と会議規則に食い違う規定があれば、体系上の破綻が生じる。
今行っている作業は、町条例の体系の中に議会基本条例を組み込み、どこから見ても、その書き方も全部整合性がとれ、かつ体系的な破綻が生じないよう言葉を選び、用語を統一しようというもの。この作業には、各条例や規則の改正がともなう。これは、実務的な作業にも見えるが、大きな意味をもつと考える。これに協力いただいていることには頭が下がり、深く感謝している。
条例には、当然、さまざまなリンクが張られている。他の条例に規定があるものは、そこを参照するようになっている。規定の根拠を他の条例で示す場合もリンクが張られる。しかし、議会基本条例の多くは「その他必要な事項は議長が別に定める」という規定が多い。この規定が必要なケースはあるが、他の条例にきちんとした規定があるのであれば、それを踏まえて書くべきなので、何でもかんでも「その他必要な事項は議長が別に定める」ですますのはよくない。
今日も3時間かけて意見をいただいて修正を加えたが、直すべきところがたくさん生じた。条例の書き方については本を買ったので、今後、勉強しようと思っている。条例の作成は、コンピューターのプログラムを書くのと同じ楽しさがある。頭の中にリンクの森ができる。ここを触れば、ここをこう変える。それもまた楽しい。


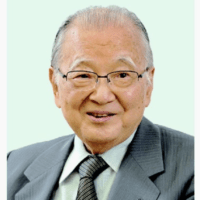







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません