議会だより、101号完成
議会だよりの最終校正。何度も何度も全文を読んで記事に誤りがないかを調べる。それでも見落としがあることが多い。いったい新聞はどのようにして、誤りを克服しているんだろうか。複数の目で見るから大丈夫ということだろうか。
訂正がないようにしたい。最後はこの一点に思いが集中する。今日の作業で新しい議会だよりが出来上がった。受け取る町民のみなさんがどういう反応を示してくださるのか。楽しみでもある。
午後は事務所で会議。会議終了の姿をイメージして会議を進めるという形を取り始めている。ただ、困難なことについては、かなかな話が深まらない。これをどうするかというのは、なかなかの課題だ。こういうことを進めるために『会議の教科書』『考え方の教科書』『頭のいい人が話す前に考えていること』という本を読んでいる。
これとは全く関係がないが、放送作家の本『トークの教室』が面白かったので『深解釈 オールナイトニッポン』という放送作家が語る本も読んでいる。最近読んだ本では、脳科学の本『「頭がいい」とはどういうことか』が面白かった。
オープンダイアローグを論理的に深めるために買った本『オープンダイアローグとは何か』も読んでいる。
『考え方の教科書』は、自分が実際に行っていることを整理して提示してくれる側面がある。この本は『会議の教科書』のシリーズ本で、考えはどう知れば深まるかという観点で書かれたもの。新たに得たことをぼくなりに整理してみよう(カッコ内は『考え方の教科書』による表現)。
①問いを立てる(問いを書き出す)。
②問いを探究する順番を決め考えを進めていく(考えるべきことに順番をつける)。
③問いを探究する(問いに対する答えを出す)。
④できるだけ具体的にイメージして深める(「具体的には?」「なぜ?」で思考を深める)。この4つのことを展開し、探究していけば、考え方が深く立体的になる。
ぼくは②についてはあまりしていない。行き当たりばったりのところがある。②を具体化すればさらに効率化が図れるだろうか。
本を読んでいると、問題意識をもって本を読むことによって、新たな認識を得て、それが力になって考えが深まると書かれていた。
自分の現時点での認識を広げる努力をしないと、新しい視点が手に入らず、考え方も平面的なままになる。問題意識をもって取りかかりつつ、本や資料を読むことによって、物事を立体的に、イメージ豊かに把握できる。ぼくはこれをいつも繰り返している。質問を準備するときは、ここから始まることも多い。『考え方の教科書』でも「考えること」は、ここから始まることが多いと書かれていた。自分のしていることが、本に書かれているということだ。面白い。
では、この本から何を学ぶのか。エッジを立てて学び取る努力をしないと身につかない。ハウツーものは、自分の行動原理に取り込まれて始めて生かされる。
ハウツー本を身につけるためにはレッスンが必要だと思っている。そのためには、反復練習を自分の中に取り込まなければならない。
今日は大谷小学校で行政報告会。これで3回目。聴衆には男性が多かった。最初の30分は町長による説明。聞くのは3回目なので、資料に対して具体的に考える作業をしてみた。
町長のアンサーの中に、コミュニティバスには補助金がつくけれど、ドア・ツー・ドアのタクシーには補助金がつかないというような説明があった。そのときぼくは優良賃貸住宅について「捕らぬ狸の皮算用」をしていた。しかし、町長のこの言葉に触発されて、頭の中が?????で溢れてきたので、携帯で検索してみた。
町長の説明は、タクシー料金への補助の話だろうか。コミュニティバスへの財源の手当は特別地方交付税しかない。ドア・ツー・ドアの乗合タクシーにも特別地方交付税による財源手当はあると思ったのが?????の原因だった。



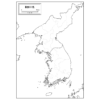






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません