今日の「潮流」は面白かった
12月19日付けの赤旗日刊紙の「潮流」にかなり心が動いたので引用してみたい。
個人の尊厳と社会正義、平和を求める市民と野党の共闘の時代。その発展を目指して、対話とは何かを考える機会が増えました▼まず思い出すのは、作家の小野正嗣(まさつぐ)さんの言葉です。「文学を理解するためには、その世界の中に入らねばならず、自分の一部を譲り渡して他者を受け入れることが必要で、つまり自分が変わるということだ」と。「文学」を「相手」と置き換えれば、対話の本質が見えてきます▼『不寛容の本質』を著した社会学者の西田亮介さんは、社会通念や先入観によって人がいかに事実を見誤っているかを指摘し、相手を理解しているつもりが実は自分の枠にはめこんだだけである危険性にも言及しました。肝要なのは「現実を直視すること」と訴えます▼本紙に連載小説を執筆中の山崎ナオコーラさんは「分かり合える相手としか通じ合わない世界は息苦しい。理解できなくても、ただ一緒にいて、話ができる、聞いてもらえる、そんな空気が広がれば、世界も風通しがよくなるのではないか」と語っています▼「言葉は、半分は話す人のものであり、半分は聞く人のものである」とは、フランスの哲学者・モンテーニュの言葉。互いの言葉を傾聴し、自分と他者がまじり合うことで対話は成立し、人と人はつながるのでしょう▼街で学園で職場で、新しく人と出会い、言葉を交わせば、発見が満ちています。異なる立場から世界を見ることは私たちの認識を深め、同時に差異を超えて共感する喜びもあるのではないでしょうか。
「肝要なのは『現実を直視すること』と訴えています」
相手と意見が合わなかったら、多くの人は受け入れがたいと感じ、反論したり反発したりする。そうではなく自分と意見の違う相手の話を聞く努力をして、自分の考え方とは違う意見を楽しむということに通じて行く必要があると思っている。そうは言ってもできるときとできないときがある。意見の違う場合でもじっくり聞いてみようという心構えでいるときは、冷静に対応することができるのだけれど、そういう心構えができていないときには、反発や反論をしてしまう。
相手の意見を聞きながら、それに対して理解を示しつつ、一旦受け入れてから言葉を返していけば、深い対話になる時がある。表面的な反発ではなく、ふところ深く受け入れつつ、違った視点で考え方を提示するというように対応できれば、相手も受け入れてくれる場合がある。
「『不寛容の本質』を著した社会学者の西田亮介さんは、社会通念や先入観によって人がいかに事実を見誤っているかを指摘し、相手を理解しているつもりが実は自分の枠にはめこんだだけである危険性にも言及しました」という下りも示唆に富んでいる。そう「自分の枠にはめこん」で理解している気持ちになっていることも多い。
「現実を直視すること」とあるが、それは「事実をありのままに見る」ということに繋がっている。自分の問題意識をもって物事を見ると本質に近づける場合もあるが、問題意識が障害になって、本質に近づけない場合もある。問題意識そのものは大切だと思っているが、自分の問題意識に合わない場合でも、丹念に事実を見ていけば、自分の問題意識そのものに誤りが含まれていることに気がつくこともある。そのときは、自分の問題意識が打ち砕かれて問題意識が解体され、再編される。結局、こういう変化は、「事実をありのままに見る」ということによって引きおこされているともいえる。
自分と意見が違うことを楽しめるようになれば、考え方に幅と深さが生まれてくる。自分の前提を疑うこと、自分の考えをも疑うことという視点も「事実をありのままに見る」ことと繋がっている。
「異なる立場から世界を見ることは私たちの認識を深め、同時に差異を超えて共感する喜びもあるのではないでしょうか」
さあ、意見の違いを楽しもう。そのことを踏まえたうえでわかり合い共感し合えるようになれば、そこから新しいものがきっと生まれてくる。



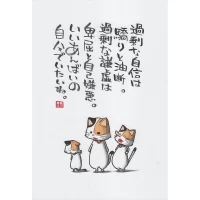






ディスカッション
コメント一覧
寛容性
理解できなくとも認め合う社会。これは、本当に必要だと思います。
顕著なのがLGBTのマイノリティーを認める機運は出来上がりつつありますね。
ただ、共産党の寛容性は自民・公明打倒の目的の為に方法論として他党と組むのであって
他党の理念を寛容してのものでは無いですよね(笑)
また、他党もしかりですが・・・・