2017年をふり返って
2017年。ぼくの思いつくまま書き綴ってきたブログにお付き合いいただき、ありがとうございました。
2005年から始めたブログは、12年になろうとしています。
日記をほぼ毎日、書かさず書いてきたことには、値打ちもあると考えています。
1)文章を自在に書く力が身についたこと
2)文章を書くことによって、考えを深められるようになったこと
3)書き続ける楽しみがあること
などブログを書き続ける効能というものがあります。
LINE全盛時代になり、感情をスタンプや絵文字で表すようになる中、文章だけで相手に自分の感情を伝えるという形式が、後継に押しやられ、文字と言葉の力が低下していると思います。絵文字やスタンプがなかった頃は、ひたすら言葉による表現で気持ちを伝えるために、文章力を磨こうとしていたのではないでしょうか。それが文章力向上の力になっていたと思うのです。
文章を自由自在に書けるようになること。これをテーマに2018年も努力をしたいと思いますので、よろしくお願いします。
1年をふり返って、書いておきます。
2017年は、一言でいうと「忙しかった」ということに尽きる。議員という仕事の上に地区委員長という仕事が重なってきて、議会広報の原稿を仕上げることと、地区委員長として会議の準備や資料の作成などが重なった。衆議院選挙のときは、衆議院事務所の責任者になったので、地元で議員の活動をすることがほとんどできず、自分としては内部矛盾を抱え込んでしまった。
いつも一定のジレンマの中にあった。党の仕事に対して責任を果たしているので、「まだこれでいいか」という思いがあったので、奇妙なバランス感覚があったが、結局、自分へのしわ寄せは、全部自分で解決する必要があったので、解決し難いことにも向きあうこととなった。
昨年で特筆すべきなのは、衆議院選挙だろう。野党共闘の実現と日本共産党の躍進という2つの任務を背負って努力した。野党共闘という点では、紀北地区は、市民連合の推薦と社民党の推薦、自由党の応援という形で、党の公認候補に対して、心温まる支援をいただいたが、日本共産党の躍進は実現できなかった。
希望の党という戦争法や共謀罪賛成の政党が結成され、ここに飲み込まれる形で民進党が解体し、潰されかかった野党共闘の流れは、立憲民主党の誕生とそれを支援した日本共産党の努力によって息を吹き返し、立憲民主党の野党第一党への躍進という形に結実した。しかし、その動きの中で日本共産党自身は後退した。
日本社会の中で、日本共産党そのものについて、さまざまな誤解や攻撃がある。その攻撃の中で、党の「縮こまり」状態は、克服できていない。日本共産党への壁は、小さくなっているが、国民の日本共産党への認識が大きく改まっている訳ではない。日本共産党そのものについて、攻撃によって生まれた誤解や認識を解きほぐして、日本共産党そのものへの理解を深める努力が必要になっている。
この活動を、どれだけしなやかに、大胆に広げていくことができるのか。ここに知恵と力を尽くして、日本共産党を大きくすることが求められている。
そのために、多くの人々と一緒に考えるための「集い」を開きたいと思っている。選挙のとき、集いを開き、12月にも集いを開いた。テーマは憲法を中心としたものだが、一緒にものを考えるような集まりを数多く開きたい。年末、集金に行った先で、「東芝さんを囲んで学習会を開いたらいいね」という声が出たので、そういうことを具体化したい。
さて。
12月末に行われた県民要求研究集会で買ってきた友寄秀隆さんの『「人口減少社会」とは何か―人口問題を考える12章』が示唆に富んでいた。日本の人口現象がどうして起こっているのかを少子高齢化という視点だけでなく、日本の資本主義の矛盾として、もっと幅の広い問題としてとらえ直す力を与えてくれている。和歌山県の人口減少は、誰の目にも見えるようになり、地域の衰退はかなりの規模で起こり始めている。人口がどんどん増え、産業が発展していくのを単純にいいとは思っていないが、ぼくたちの住んでいる地域は、明らかに地域崩壊の方向に向かいつつある。
「今まで人口が増えすぎたのだからちょうどいいようになるのではないか」
というような減少として、人口減少が起こっているのではなく、地域そのものが持続できないような形になりつつある。
この問題に向きあわざるをえないが、人口減少をどう考え、どう立ち向かっていくのかは、容易ではないだけに、きちんとした学びを基礎において、ものを考える必要がある。
今年は、そういうことを考えながらの年明けとしたい。





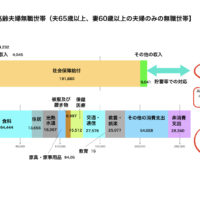







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません