時代を読み解く論理

史的唯物論と言っても何のことか分からない人が多いだろう。唯物論という哲学の考え方を歴史の分野で生かしたものだが、史的唯物論はむしろ、この論理が作られる過程によって、唯物論という哲学のものの見方が確立したのだという。言い方を変えれば、人間の歴史の研究及び、当時の現在の政治分析の中で唯物論が確立したということだ。それほど唯物論にとって、社会の歴史研究の意味は大きかった。つまり、唯物論と弁証法的なものの見方が確立したのちに、この理論を活用して人間の歴史を研究したということではないということだ。
唯物論は、人間の意識や人間の社会的意識の根源は客観的な物質にあると捉えてきた。今やこの考え方は脳科学の発展によって、より詳細に明らかになりつつある。人間の脳は、母体の子宮の中で胎児の皮膚がふれる子宮の壁から得られる刺激を通じて形成される。外界に対する能動的な反応によって、脳や意識が形成されていくことが、詳しく克明に明らかになりつつあり、この発達の仕組みをふまえれば、AIによって脳が作れる時代が来ることが予感されている。ペレットで培養された脳細胞が、外界からの刺激によって積極的に反応する仕組みを利用すると、この細胞はブロック崩しゲームを実行できることが明らかになっている。この技術が発展すれば、人間の作った細胞によって脳をつくることができる未来が見える。
物質の外界からの刺激による反応と脳の反応とは一つの線の上で起こってる。細胞や脳の発達によって人間の意識は生まれてくるのであって、最初に魂があって人間の意識ができるのではない。唯物論は、こういうことを明らかにしてきた。こうであるならば、人間の社会における意識も、人間の意識の外に客観的に存在している自然や社会的な諸関係によって生成されることになる。個人の意識が先にあって社会的関係がつくられるのではなくて、やはり人間の社会的意識も社会的関係による反映がその根底にあるということになる。
もちろん、個人は自由な意思を持っている。外界からの反応を積極的に受け入れ、その刺激によって形成されてきた意識は、ある段階になると自我をもつようになる。我思う故に我あり。その人間がその人間であり続けるのは、形成された自我が維持されることによってのみ、自分は自分を確認できる。その人が自我を失ったら、もはや自分を維持し続けるのは難しい。
しかし、自我は生まれたときから備わっているのではない。それは成長という歴史的過程の中で生成してきたものだ。このことを見失うと大きな間違いに陥る。自我を突き詰めていくと「はっきりしない」問題にたどり着く。自分の意思や意識というものは、鉛筆の芯のように黒く堅いというものではない。自分の殻に閉じこもって自分を徹底的に見つめていくと、かなり曖昧なものにしかであわない。自分の自我というものは、結局は細胞の発達として目覚めた自我というものでしかない。その中心にあるのは無意識のうちから始まる反応だ。
人間は社会を形成している。人間の社会は複雑にできている。東京などの都会では、街ゆく人に人は反応を強く示さない。それは外界からの刺激があまりにも大きく強いので、情報が入ってくるのを無意識で拒否しているかららしい。そういう風に意識が働いたとしても、人間は無意識のうちに多くの刺激にさらされ、反応し続けている。このようにして形成される社会的意識の中には、その時代による刻印のようなものがある。
第二次世界大戦後、人類に向かって真っ先に発せられたのは世界人権宣言だった。これは人権に対する先駆的な宣言だった。この宣言は、第二次世界大戦という多大な犠牲の上で生成されたものだ。この人権宣言には、人類の苦難の歴史が刻まれている。いま世界ではジェンダー平等への大きな波と、何世紀にもわたってきた植民地支配への反省という巨大なウエーブが起こっている。同時に未来の危機である地球温暖化に対して、これを止めようという巨大な流れも生まれつつある。
人間はこのような時代の動きの中で大きな影響を受けていく。もちろん、そういうことを全く感じないで生きている人も多い。しかし、この大きな波をまったく拒否して生きていくのも難しい。人間の意識は社会的な関係を反映して形成されていく。社会的な意識は社会的な存在によって、大きな影響を受ける。ただ、多くの個性的な反応や千差万別とも思われるような解釈が生まれてくるのは、外界からの刺激に対する反応の仕方が、千差万別だからに他ならない。
マルクスとエンゲルスは、こういうものの見方、考え方をもったなかで、人間の社会をより根底から突き動かしているのは、人間の意識ではなくて、社会の経済活動にあることを見抜いてきた。その中でマルクスは、資本主義経済の運動法則を徹底的に明らかにしようと研究をおこなった。この研究は、人間社会が結局はどんな力によって動かされていくのかを明らかにするものだった。資本論によるマルクスの研究は、マルクス、エンゲルスの史的唯物論という理論を形成する大きな力になった。
政治や宗教や芸術や文化等々は、経済的な社会的土台の上にたつ上部構造を形成しており、この上部構造は、経済的な社会構造の反映という側面が強い。しかし同時に、そうやってできた上部構造が、経済的な人間関係に大きな影響を与え、下部構造である経済や経済的な仕組み、経済的な人間関係に大きな作用を及ぼすことも明らかにした。
史的唯物論は、歴史を裁断する型紙ではない。こういう社会構造の仕組みを理解した上で、実際の社会がどう動いているのかという分析においては、極めて柔軟に物事を把握し、社会情勢の分析を行うことになる。
英雄が現れて時代を動かすのではない。もちろん、時代の中で個人が果たす役割は決して小さくはない。しかし、こういう人物がこういう仕事をしたので歴史が動いたというのではない。それは現在の社会の中での内閣総理大臣のことを考えれば、見えてくるだろう。安倍さんがさまざまな役割を果たしたのは間違いないが、安倍さんが日本を動かしていたとは見えないだろう。同時代に生きていると、権力者が影響を与えていないことがいかに多いかを、同時代の中で日々確認できる。
しかし、時代小説やドラマになると、あたかも英雄の行動によって歴史が大きく動いたかのように描かれる。その時代の経済を描き、その中で人間がどう生きていたのかを描きながら時代を描いていることは少ない。
靖国派と呼ばれ、日本会議という組織や統一教会の影響や、歴史修正主義という動きが安倍さんの元にあって、日本を戦前と同じ方向へ動かそうという動きは、安倍さんの個性を超える大きな「勢力」としての動きがある。日本補選前のような国に戻そうとする動きと、アメリカの引き起こす戦争への動きには思惑の違いがあるのに、同じ方向を向くベクトルの中にある。アメリカとの利害の一の中での憲法改正をめぐる動きと執念は、新自由主義的な改革だった中曽根内閣とつながっている。
日本の新自由主義は、資本による徹底的な利潤の追求という動きと戦前への復古主義、国民主権の否定、恒久平和主義への否定、基本的人権の否定の動きとの関係で親和性がある。親和性の根底には、一方の極への富の集中と蓄積、もう一方の極への貧困の蓄積による民主主義の否定とつながっている。
戦争準備という反動的な動きが強まってきた根底には、資本主義の搾取の強まりと格差と貧困の拡大がある。ほんのわずかな一握りの超富裕層が、自分たちの利益を上げるために政治が最大限利用されている。新自由主義による資本の蓄積が、格差と貧困を広げ、一方の側に富を集中させてきた中で世界が不安定になっている。
この流れの中で、安倍さんがという個性が大きな役割を果たし、右翼的な傾向が強まった。歴史の中には、さまざまな勢力の動きがあり、流れの違うベクトルが反発したり、入り交じったり、共鳴したり、力が合わさったりしてうごめいている。そういう中で誰が歴史の表舞台に躍り出て脚光をあびるのか。そこに生きた政治のダイナミズムがある。
日本の地方自治体における首長の権限は極めて大きい。ぼくの住むかつらぎ町でいえば、最も地域に大きな影響を与えているのはかつらぎ町という自治体組織であるのは間違いない。しかし、この組織の外に農業があり商工業や医療、福祉の仕組みがある。いろいろな会社や個人商店があり、それらによって地域の経済力が形成されている。この中に地域住民の生活がある。
分かりやすい地域は、巨大な企業が存在する地域だろう。こういう地域に行くと地方自治体の影響力は相対的に小さくなる。地域の分析と言っても、巨大な企業のある地域とない地域では、自ずから分析に視点が違ってくる。
ぼくの住むかつらぎ町は、巨大な企業による城下町は形成されていないので、主要産業の分析とともに、最も影響を与えている地方自治体の分析が重要な意味をもつ。地方自治体の分析の出発は、首長がどういう施策を講じているのか、首長の性格も含めて分析することが大事な意味をもつ。それは、たった一人の個人に圧倒的に権限が集中しているので、個人の果たす役割が社会的に大きな影響力をもつからに他ならない。
住民運動が世の中を大きく動かすのは、主権者に選挙権があり、その主権者を中心とした運動が世論を形成し、大きな影響力を与えるからだ。経済的な位置の違いによって階級が形成されているので、支配されている位置にある国民の運動が、支配している位置にある人々にすべて見えているわけではない。支配される側は支配している側の人間関係や動きの多くを知らないし、理解できない。
資本主義社会のもとでは、人間と人間が階級に分裂している中で分断されている。分断の中で支配者の生き方と多くの国民の生き方は大きく分裂している。支配者の側に競争の中でのし上がって行く人々は、支配者が身につけている文化を学び、真似をし、支配者の側が身につけているものに興味を持って、自分たちをその文化の中に溶け込ませている。
自民党の政治家が、庶民とは全く違う金銭感覚をもち、庶民の暮らしを理解できないように見えるのは、政治家たちが世間に晒されている存在だからだ。人間としての動きが閉じられていないので、国民は、政治家の動きや姿を通じて、かけ離れた世界に生きている人々であることを垣間見ることができる。今、国民の目の前で暴露されつつあるパーティ券のキックバックの姿は、いかにお金の扱いとお金に対する意識が、庶民とかけ離れているのかを教えてくれる。こんな感覚を持った人間集団が、格差と貧困の中で苦しんでいる人々に対して寄り添うことはない。むしろ、そういう人々と自分たちがいかに違うかを日々確認しながら、生活していると言ってもいい。
「我々高級な人間集団とつきあいたいのであれば、既製品の背広など着るな。少なくとも一着30万円の服を着れ」
階級意識の中には、そういう文化が存在する。
東京に行くと、高級な人々は自分たちと一般人を区別し、一般人のことを「パンジー」と呼ぶ。和歌山県では県庁に勤めているような人は、少し生活水準の高い人々ということだが、東京では「パンジー」と呼ばれる。
このような社会の中で、国民は自由と民主主義を獲得してきた。その結果、自分の人生を自分で選び取ることのできる道も開かれてきた。資本主義社会の支配は、奴隷制社会のように、人間の生殺与奪の権限を支配層はもっていない。支配といっても支配者がコントロールできない部分がある。奴隷制、封建制、資本主義という歴史の変化・発展の中で、国民はかけがえのない権利を獲得し、自由を拡大してきた。今日の国民運動は、この自由獲得の上に立って行われているものであり、日本に生きる国民は、自分たちのたたかいによって、未来をより民主的で自由を拡大できる力をもつに至っている。
戦後の民主主義は、すべて国民の力で勝ち得たものだとは言い難いかも知れないが、戦前の命がけのたたかいというものも引き継いで今日がある。戦争を通じて日本国民が手に入れた恒久平和や憲法9条への意識は、歴史的に形成されてきたものであり、根底には膨大な人間の犠牲の上に培われた意識がある。同時に戦後の日本の民主主義には、日本国憲法を武器にしてたたかい取ってきた成果がある。たたかいによって国民の中に定着してきた成果がある。
日本国憲法をめぐるたたかいでは、戦後の民主主義が試されており、同時に敗戦によって決着がついていない戦前からの強い糸とのたたかいという側面をもっている。日本の権力を握ってきた勢力は、教育を通じて国民に権利を教えることを阻んできた。自分たちの力で政治や社会を変えることがでえきるということを教えない教育を重ねてきた。多くの人間が労働者になるのに、労働者になったときに行使できる権利さえ教えないで、社会に送り出すことが当たり前になっている。私たちはこういう社会に生きている。支配されてきた人間がたたかいによって勝ち取ってきた民主主義と自由は、国民の運動として次の世代に引き継がれなければならない。目覚めよ、若者。こういう働きかけが大事になっている。
階級闘争によって時代が切り開かれる。住民の中での運動と議会のなかの活動を結びつけて世の中を変える。こういう考え方で日本共産党は活動している。社会の動きを今日書いたことなどを念頭に置いて分析し、立体的に捉え直すのは面白い。




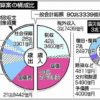






ディスカッション
コメント一覧
俺はやっぱり魂は存在すると思うんですよね。
人間死んだら天国に行くんですよ。そして神の裁きを受けて悪い事をした人間は地獄にゆき正しい事をした人間は天国に行くんです。間違いありません。俺が保証します。
いいですね。天国に行って会いたいのは母親ですね。父にも会って戦争のときの気持ちを聞いてみたい。
ただ、人間の意識は、外部への能動的な反応の積み重ねによって形成され、生まれてくるというのも面白いと思っています。無機物の反応も、植物の反応も、動物の反応も基本的には同じ。その中で意識が生成されていくという論理も面白いです。実際にそういうプログラムを組んだロボットが、次第に起き上がって歩けるようになる様を見ていると、その先に意識の芽生えがあるのだと思います。ほんのわずかな脳細胞に刺激を与えると、ブロック崩しのゲームができるようになるという実験も面白いものでした。
唯物論の講義、素晴らしいです。唯、わたくし、出身学校の講義ではドイツ観念論に最も感銘を受けました。観念論サイドでは、主に現代の支配的な言語哲学と対峙するなかで、自己意識は存在すると主張するようです。此処に自己意識は存在する。決して無くならないと。マルクスは恐らくヘーゲルの影響も受けていますかね。その影響を脱して、自らの哲学を作り上げた。ヘーゲルはキリスト教学者ですから、自己意識すなわち魂だと考えて良いと思うんですが、如何でしょうか。私も不勉強でその辺り全く分かっていないんですが。
私も、ではなく、勿論私は不勉強、が正しいでした。
ぼくは、魂があればいいなと思っています。輪廻転生ができれば嬉しいですね。もう一度人生が楽しめればと思います。生前の記憶がなくても、あるときから自分の人生が始まって、また新しい時代に生きることができれば面白いのになあと思います。
霊魂の存在を信じているのは、キリスト教も神道も同じような感じですね。お釈迦さんそのものは、唯物論に近かったと思います。したがって元々の仏教は霊魂の存在を認めていなかったのではないかと思います。浄土真宗は霊魂の存在を否定しているようです。
アルツハイマー型認知症の人が身内にいました。親しかったはずなのに「どちら様」と言われました。昔の記憶は海馬を通じて脳の後ろの方に格納されているのに、20年前ぐらいの新しい記憶(発症する前の記憶も失われます)がなくなってしまいました。こういう状況を見ていると、人間の記憶は脳が病気に犯されたら壊れるのを感じました。
脳が壊れてしまうと、自分自身を認識できないというのは、いったいどういうことなのかということを考えざるを得ないと思っています。
人間は脳の助けを得てものを考えているかどうか。
人類が誕生する前に地球はあったと考えるか。
あなたは他人の存在を認めているか。
などの問いに対してどう考えるかということが、霊魂を信じるかどうかの分岐点の質問になるのではないかと思います。
ぼくはいま、ヘーゲルの「精神現象学」を読んでいます(もちろん日本語訳です)。マルクスとエンゲルスは、ヘーゲルの弁証法に大きな影響を受けていました。少しはヘーゲルから学びたいなと思って手にしました。文庫版のかなり分厚い2冊の本です。読んでも分からないことがたくさんありますが、「100分で名著」の純粋理性批判の薄っぺらい解説書を読んで、この本を読もうと思い立ちました。ヘーゲルが弁証法をどうとらえていたのか、知ることは有意義だと思っています。観念論だから駄目とかいうのはなくて、哲学者が何をどう考えたかに寄り添うことが、物事を考える力を身につけてくれるのではないかと思っています。
ただ、哲学を学ぶときに必要なのは、自分はどう考えているのかという基礎が大事になると思っています。ぼくの場合は、18歳で唯物論と弁証法に出会い、その分野をかなり深く学んできたので、いまもこの考え方が基本になっています。この哲学に基づいて、精神とは何か、意識とは何か、唯物論とは何か、弁証法とは何かという視点で、観念論とは何かという点についても学んできました。自然科学と社会科学の成果の上にたって、たえず変化していく唯物論と物質の研究によって不断に内容が豊かになっていく弁証法は、開かれた終わりのない体系なので、いいなと思っています。
哲学の学び方の中には、この哲学者はこう言っている、あの哲学者はこうだというように知識として学ぶという方法があると思います。しかし、このような学び方は、思考の相対主義化だと、ぼくは思っています。これでは真理がどこにあるのか分からなくなります。
哲学を学ぶためには、批判的精神と真理を探究するという精神が必要だと思います。その中で物事を考えるべきだと思っています。ただ、哲学者の具体的な議論は、なかなか面白いのではないかと思います。
脳が壊れてしまう事と魂の不在とは関係ないと、俺は考えます。
すみません、不勉強なのでウィキペディアに頼ります。理性概念として、神、魂の不滅、自由が挙げられる。理性概念の問題は実践理性批判で展開される。自由、魂の不滅、神、これらはみな証明されえず、認識の対象ではないが、しかし実践理性批判ではこれらの概念を前提し、己の法則を立てる。魂の不滅、あるいは永世の前提のみが無限の進歩を可能とする。道徳論を幸福論と名づけうるためには、宗教だけがわれわれに与えるとしてこの最高善を促進すべき希望が必要となる。したがって証明されなかった神は、いまや実践理性として、そのような不死なる魂へ報償を与えるものとして要請され、体系の中へ位置づけられる。これはこうらしいですが、唯物論は全く違いますものね。
法然は言っているようです。どれ程周囲に雑草が蔓延ろうと、水面に必ず月は映る。浄土に魂は救済される。雑草すなわち雑念や、脳が壊れることになっても、南無阿弥陀仏と唱えれば救済されると。
「魂の不滅、あるいは永世の前提のみが無限の進歩を可能とする」という点をもう少し展開してみて下さい。魂が不滅なので、進歩が保障されるという意味でしょうか。魂がずっと続くので、魂を通じて学習が蓄積されていき、人類は進歩するのだという意味でしょうか。
すみません、学生時代のテキストにカントの宗教に関しての項がなく、残念ながらお答え出来ません。が、ヘーゲルは宗教の本質を民族精神の一契機としての民族宗教と規定し、その基準として、主体的宗教と公共的宗教という条件を挙げます。宗教は単に個人の魂の救済のみに関わる私的宗教であってはならず、国家など社会生活のすべての面で民衆と結び付く公共的なものでなければならない。民族宗教の基準のもとに現実のキリスト教を吟味し、教義や儀式が僧侶や教会によっていかに民衆に強制され、それ故いかに非道徳的非人間的であるかを指摘。ヘーゲルも宗教批判をやっているのです。そしてキリスト教をドイツの民族宗教として再興する道を歴史的展望において示そうとした。キリスト教論の立場を実践理性の自律(カント)から愛の合一に転換した。実践的活動は客体を無化し、全く主体的である。ただ愛においてのみ人は客体と一つになり、客体は支配することも支配されることもない。つまり麻薬ではないということでしょうか。
久保陽一氏 ドイツ観念論への招待、からの引用です。
イデアリスムスは、事物の原型や規範としてのプラトンのイデアが近代哲学において、人間の心に内在する事物の似姿としての観念という意味に解釈されたもの。ヘーゲルの場合、イデアリスムスのもとにプラトンのイデア論に近いいわば存在論的な理想主義が無限者の原理という意味で考えられていた。イデアとは有限と無限との総合であり、イデアリスムスは有限者を真に存在するものとは認めない立場である。そういうものとして、あらゆる哲学は本質的にイデアリスムスである。答えになっていますかね。なってませんね、すみません。不勉強なので。
hurukawaさん、書いていることを申し訳ありませんが、解説的にかみ砕いていただけないでしょうか。「イデアリスムスは有限者を真に存在するものとは認めない立場である。そういうものとして、あらゆる哲学は本質的にイデアリスムスである。」という意味を知りたいですね。
ヘーゲルの宗教批判を読んで感じるのは、宗教は教義がありキリスト教には聖書がある。聖書は、waoさんが書いているように、ヨーロッパの文化などを知ろうと思えば、聖書を読まなければならないというのは、その通りだと思います。それほど、深く大きな影響を与えているものだと思います。
ただ、教義というのは、どうしても時代の進展とともに合わなくなってくるものだと思います。もちろん、科学も同じく過去に明らかにした法則は、研究によって覆されていく運命にあると思います。科学が開かれた系だというのは、歴史の進展とともに研究が進めば、解明された真理に席をゆずっていくことを、いわば当たり前のこととして、最初からそれを含んでいるということです。
しかし、宗教の教義というものは、個人や宗派が過去に語ったもの、規定したものは、時代の進展の中であわなくなるのに、なかなか変えられない仕組みの中にあると思います。教義や経典が閉じられた系という側面をもつのは、致し方なく、したがって時代とともに宗教も変化せざるをえない中にあり、さまざまな宗派へと分かれざるを得ないものだと思います。こういう考え方が今行われている話とかみ合っているのかどうかさえ、よく分かりませんが、そんなことを考えます。
余談ついでに、あれだけ権威主義的で古い体質をもつ医学が、医療の論理と技術については、研究に貪欲で絶えず大きな変化を受け入れる体質をもっています。接骨院系の東洋医学的な論理は、人間の体全体をつながりの中で把握し、接骨院でしか治せない分野もあると思っていますが、日本のこの分野は、先生1人に1人の論理があり、やっていることが院によって大きく違います。こちらの業界は、医学界のように新しい解明を集団で共有する仕組みがないので、バラバラになっています。知識と技術の共有、医学界や科学の世界はその点が優れていると思います。
真理だと思っていたものが、時代の進展とともに否定され、進化していくのは、人間の認識が次第により深い真理へと接近していくからです。極め尽くすことのできない物質の真理に対して、一歩一歩人間は歩んでいきますが、この過程は絶対的真理に対して次第に近づいていく不断のプロセスであり、現時点で真理だと思っているものは、絶対的真理の粒を含んだ相対的な真理だと捉えられると思います。
すみません、私は観念論の講義には明らかに不適格です。またドイツ観念論の独自の用語を使わなければ、説明不能かもしれません。言語サイドがドイツ観念論を言語的に解体する試みを行ったようですが、無意味だったみたいです。さて、一般的科学とは少し違って、哲学は最新のものが常に正しいとは言えないように思います。19世紀半ばから20世紀初めにかけて、初期マルクスの自然主義、エンゲルスの唯物論等によって観念論批判が行われました。外的な物体を意識や精神に依存するものとみなす考え方に反対し、意識の外に対象が存在することを認めています。しかしドイツ観念論はすべての対象あるいは対象すべての面が意識や思考の産物であると言っていません。通常の意識において対象が意識と関わりなく存在し、したがって恣意的想像の産物などではなく、客観的に存在すること自体は否認されていません。ドイツ観念論は世界の成り立ちを自我、自己意識、理性、精神と呼ばれる精神的なものから説明する立場であって、外的な物体や自然を原理とする実在論や唯物論と対立はします。カントの実在論は観察可能な現象と数量的要素への還元に基づいて恒常的法則をみいだそうとした近代自然科学にかなったものではあります。すみません、此処までテキスト丸写しなので御容赦願います。
まず冒頭の講義はおかしいですね。観念論の説明に不適格と言いたかったのでした。またわたくしも唯物論に魅了されている一人ではありまして、新しい哲学が常に正しいとは言えないとは、唯物論否定を意味しません。そうですね、クオリアの説明に躓いているような現代の哲学は余り好みではないとは言えるでしょうか。
間違っているかも知れませんが、イデアといものと概念とは関係が深いと思います。簡単な例でいえばリンゴという言葉から人間はリンゴをイメージします。現物リンゴは、実は千差万別で種類も多い。富士もあれば、サンふじ、王林などたくさんあります。リンゴといえば赤い色を思い出す人も多いと思いますが、リンゴの中には青リンゴもあります。ぼくは、ツルツルテカテカのリンゴが好きでした。種類は分かりません。最近はふじかサンふじかですね。
具体的な言葉であるリンゴは、目の前にある具体的なリンゴを意味する場合もあれば、リンゴからイメージされる概念としてのリンゴもあります。唯物論でいう概念は、唯物論的な基礎をもつというように理解されています。具体的なリンゴというものがあって、そこから概念としてのリンゴが認識として生まれてきますが、それらの概念は、具体的なリンゴという存在を通じて、認識されるということです。概念のリンゴは、個別的なリンゴという存在を通じて導き出される一般的なリンゴで、リンゴのさまざまな要素を兼ね備えたものですが、それらの認識は、個別的なリンゴを通じて導きだされた一般的な概念で、リンゴというものの本質を反映したものです。
唯物論は、概念というのは、個別的で具体的なものから導き出された一般的な認識だが、この一般的な認識は、リンゴの本質により接近する認識になるということです。
現在のリンゴが全部滅んで、ふじだけになるとリンゴの概念もふじに統一されますが、今の種類の多さからいえば、リンゴという概念は人によってそのイメージが大きく違うということです。リンゴ農家のいうリンゴと和歌山県人がもっているリンゴのイメージはものすごく違いがありますよね。概念で物事を論じはじめると、概念のもつ意味の違いによって、論議が食い違うことが多々あります。したがって科学的な議論を行う場合、概念の統一が大事になります。
おそらく日本人のブドウに対するイメージとヨーロッパでワインを盛んにつくっているところのブドウのイメージは大きく違うでしょう。概念というのは、そういうものだと思います。
ちょっと信じがたい世界になるんですが、プラトンのイデア論について書いておきます。テキストが見つからないので、ウィキペディアに頼ります。我々が肉体的に感覚する対象や世界とはあくまでイデアの似姿にすぎない。で、中期イデア論。学習というのは実は想起である。つまり我々のプシュケー、魂というのは不滅であって輪廻転生を繰り返しており、もともとは霊界にいてそこでイデアを見ていたのであって、こちらの世界に来るときにそれを忘れてしまったが、こちらの世界で肉体を使い、不完全な像を見ることによりイデアを思い出しているのだ。それが学習ということだ。この想起の考え方によってプラトンは、不知な対象は探求は不可能だとする探求のパラドックスは間違っているとする。プラトンはphilosophy愛知というのはまさに死の練習なのであって真の愛知者とは、出来る限り自分のプシュケーをその身体から分離解放しプシュケーが純粋にそれ自体においてあるように努める者だとする。そして、愛知者のプシュケーが知る対象として提示されるのがイデアである。
全く勝手な解釈ですが、具体的事物からえられる本質と思われる概念(簡単な例で言えば、具体的なリンゴとこのリンゴから得られるリンゴのイメージ)の方が、何の傷もなく、凹みもない綺麗な形をしているように見えます。プラトンは、このようなところから、現実世界として見えるものは「我々が肉体的に感覚する対象や世界とはあくまでイデアの似姿」だと考えたのではないでしょうか。
なぜ、具体的事物から抽象される概念の方が、完璧なものに見えるのか。それは、現実のさまざまな完全でない複雑な要素が、捨象されて本質だと思われるものだけが取り出されて見えるからに他ならない。イメージが本質で現実は、本質の似姿だという逆立ちした捉え方はここから生まれるのではないか、と思います。
科学は、現実世界の複雑なものから法則を見いだすときに、具体的事物を一生懸命分類して、より分け、複雑に絡み合った要素から、本質だと思われるものと取り出して研究してきました。したがって実験は、不純だと思われるものを取り除いて、シンプルな形にして、その関係をしらべ、ここに法則があるということを積み重ねてきたのだと思います。
このような研究のプロセスは、科学の発展にとっては、どうしても必要なものでした。しかし、それは具体的な連関と連鎖を切り離して研究するという道でもありました。その結果、法則だと思ったことが、新しい条件(捨象していたもの)を付け加えると、成り立たないことが見えてきて、法則が覆されることが繰り返し起こしました。ニュートン力学とアインシュタインの相対性理論との関係のように。
自然科学の発展は、単純なものから複雑なものへと認識を広げてきたと思います。気象学などは、複雑系とよばれていて、なかなか気象の変化を具体的に把握して予想するのは、かなり困難を極めます。何によって変化が起こるのかを見極めるのが難しいのは、さまざまな要素が影響し合っているからです。日本の場合、毎日晴れと行っていれば、60%以上の確率で正解となりそうですが、これをさらに70%、80%、90%と予報を高めていくところに科学的な営みがありそうです。
プラトンの話に戻れば、具体的な事物から捨象して本質的なイデアを見いだして、このイデアに真実があるという見方をしたのだと思いますが、そこからずいぶん時間が経って、人間の認識は、具体的な事物の具体的把握にそって、科学を発展させてきたようにも思います。デジタル技術が発展し、人間の作った画像が本物に見えるためには、汚れや劣化を表現しなければならないということになっています。技術の発展によって、現実に映像を近づけていますが、そのようなことができる技術は、まさにデジタル技術とデジタル技術に付随する科学の発展によって手に入れたものだと思います。
waoさんの話を聞いてみたいですね。深い話が出てきそうです。
ここのトピックが、唯物論なのですが、日本共産党が人気が無いのが此の唯物論のせいではないかと思う訳です。唯物論のイメージは無機質な冷たい印象を人々に与えておるのじゃないか。俺の日本共産党の党員の友人は人間死んだら「無」になると主張しております。何年か前、東芝さんもそうではなくて灰になるから「無」になる訳ではない、と書いておられましたが俺に言わせれば50歩100歩です。その論理では。で、俺は友人に「無」とはなんぞやと問うと「無」とは何も無い事だと答える訳ですよ。話にならない訳です。こんな事では党員拡大なんて無理ではないかと思います。東芝さんはまだ柔軟な発想をする人ですが、少なくない党員の方々が俺の友人の様な考え方をしています。分からない事は取り敢えずエポケーの態度でいいと思いますが、断定的に「無」になると主張するのは間違いではないかと思うんですね。俺はクリスチャンなので天国はあると思っています。それも証明してみせろ、と言われても証明出来ません。俺の尊敬している原良の支部長は「無」とか死後の世界とかいうものは「不可知論」だと言うのですが、そのような答えでいいのだろうかと思います。此の人は学校の先生をしておられた立派な人なんですが何だかそこに限界を感じます。ある専従の女の人が
「宗教は麻薬だ」
と発言したので俺はむっときて、
「日本共産党はいまだにそんな事を言っているからダメなんだ」
と怒ったんですがマルクスが確かに宗教は麻薬だ、と書いてるんですね。然し、赤旗などを読んでいると「9条の会」の賛同者に坊さんや牧師の発言が載っている。大分赤旗も変わってきたなと思います。
まあ、統一教会とかエホバの証人とかとんでもない宗教もあるから全部の宗教がいいとは言いませんよ。然し伝統(トラデション)が一応ある宗教はそれなりに認めなければならない筈です。エルサレムは、ユダヤ教、イスラム教、キリスト教を信じる人々が安心してお参り出来るようにバチカン市国みたいなものを創ったらいいのではないかと思います。
話は少し脱線しますが、哲学、文学、音楽の素養は「聖書」を読まなければお話になりません。特にヨーロッパの文学は「聖書」の素養がなければ理解出来ないですね。脱線でした。
俺は史的唯物論は詳しくないですが、面白いと思います。確かに科学的で俺もちらっと読んだだけですが、成る程と思わせられます。鉄壁の論理だなと思いますが、「唯物論」だけを切り取り考えてみると違和感を感じるのは何故かな。矢張り東芝さんの唯物論の先に唯脳論を感じるからでしょう。これも何年か前にやり合ったのですが、心、魂は脳みそにある、コレが壊れたら心、魂は無くなるのだ、と言う主張だったと思いますが、俺は納得しなかったと思います。本当に心とか魂は脳みその産物なのか。脳科学が凄まじく発達していると言っても俺の勘が結局いくら研究しても分かりません、という事になると思います。不可知論です。こうゆう意味では原良支部長の意見は正しい。矛盾した事を書いておりますが唯物論も信じるか信じないかと言う宗教に似ているではないですか。認識論で言っても唯物論はそういうふうに見えるという事であって実は夢の様なものではないかとは考えられませんか。だが、俺は例え夢であっても、切ればドバッと血が飛び出る様な生々しく素晴らしい夢なら信じたいですね。
らちもないタワゴトにお付き合いくださり有難う御座います。furukawaさんにもコメント頂きたいですね。
マルクスは、25歳の時の論文「ヘーゲル法哲学批判・序説」のなかで、「宗教上の不幸は、一つには現実の不幸の表現であり、一つには現実の不幸にたいする抗議である。宗教は、なやめるもののため息であり、心なき世界の心情であるとともに精神なき状態の精神である。それは民衆のアヘンである」(2010年7月15日付赤旗の記事から引用——いまも 宗教はアヘン 赤旗 で検索すれば読むことができます)と書きました。この文章からは宗教に対するマルクスの肯定する見方と批判的な見方の2面が読み取れると思います。引用した赤旗の記事には、「アヘンという言葉には、宗教に対するマルクスの批判もこめられています。宗教は民衆にあきらめとなぐさめを説き、現実の不幸を改革するために立ち上がるのを妨げている、という意味です。ここには、当時のヨーロッパで宗教が果たしていた歴史的な事情が反映しています。キリスト教は、国王権力と支えあう関係になって、専制支配のもとで苦悩する民衆に忍従を説いていました。マルクスはそうした宗教の役割を批判したのです。
マルクスがアヘンという言葉を使った背景には、当時のヨーロッパでアヘンが話題となっていたという事情もあります。イギリスが植民地インドで製造したアヘンを中国(清)に密輸し、アヘン戦争が起こった時代でした。」と書いています。
唯物論の精神に対するものの見方は、物質の発展の中から精神が誕生したという自然科学の歴史観をふまえたものです。意識は外界に対する反応によって形成されるということです。科学は、皮膚には色を識別できるセンサーが備わっていることを突き止めつつあります。人間の進化の過程を見ると、ウイルスに感染したことによって、脳が発達したことや、哺乳類に子宮が誕生したのもウイルスへの感染があったとか、がん細胞なしに人間は誕生できないとか。男性のもつY染色体が次第に縮みつつあり、やがてなくなるとみられているとかいうことが明らかになりつつあるます。こういう話は驚きの連続であり面白い。
人間の意識は、脳によって生まれているだけではなく、人間の体全体が外界からの刺激を受ける中で、脳に信号が送られ形成されるので、人間は脳だけで物事をとらえているのではないことが明らかになりつつあります。また、脳は、ほとんどの情報を潜在意識下で処理しているので、意識する前にすでに判断していることも明らかにされつつあります。潜在意識下での情報処理という仕組みを知ったので、たくさん資料を読み込めば、脳が勝手に自分の知らないところで処理してくれるということなんだなと思い、その仕組みを活用しています。
一般質問などは、情報の収集さえ行えば、おのずから質問の組み立てはできるというスタイルを採用して、ギリギリまで情報収集をして、一気に原稿を書いています。論理の組み立てなんてことは潜在意識に任せています。町当局から早く原稿がほしいといわれはじめたので、原稿を提出してからも資料を読み込むようになりました。こういう作業をしていると、一般質問の内容がさらに変わることが分かってきました。情報を読み込んで、情報と情報の連関を把握すれば、あとは眠ると勝手に論理は組み立ってくるということです。潜在意識下での情報処理という機能は、なかなか面白いものだと思います。
唯物論というのは、精神と物質のどちらが大事かという価値の判別をしているのではなくて、精神がどのような物質の働きによって生成されるのかを、物質との関係で克明に明らかにするところにその中心があると思っています。精神と物質の根源性についての議論よりも、人間の精神は、どういう仕組みで成り立っているのか、外界からの刺激に対してどのような反応が体の中や脳の中に発生するのか。その中で脳がどのように変化するのかという突き詰めても終わりのない旅のようなもので、これを旅するのが極めて面白いというところに、その中心があるということです。
無というのは、過去にも書きましたが、自然科学の場合は、物質もエネルギーも時間も空間もない存在だと定義されます。そこから宇宙が生まれたという説もあります。では何もない無に何があったのか──これは、私たちを形成している物質ではない反物質があったということにつながっています。自然科学は、物質ではない違う性質の反物質とは何かというところに足を踏み入れています。それはそれで面白いなと思います。
ふ〜む、面白いですね。
でも物質ではない違う性質の反物質と言うものの正体を我々が生きているあいだに証明出来るのでしょうか。実際に科学的に捉えなければ観念的な学説になるでしょう。ノーベル賞を貰えなかったホーキング博士みたいに。